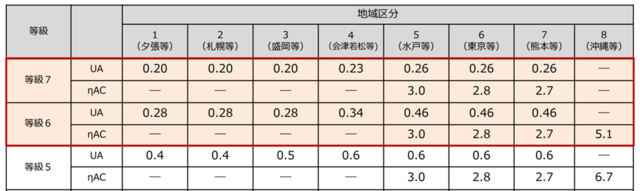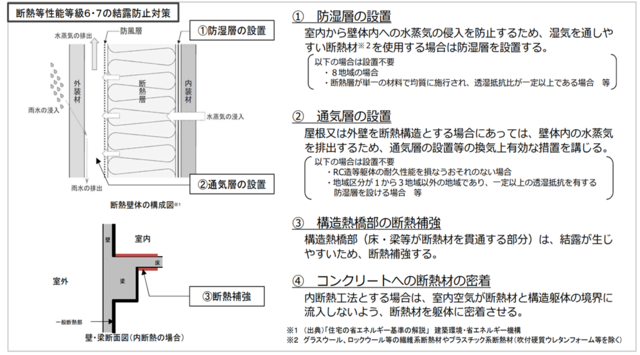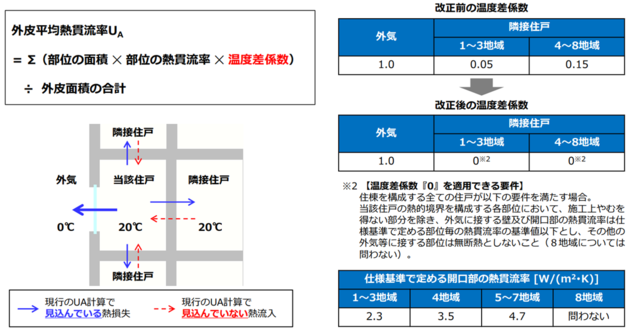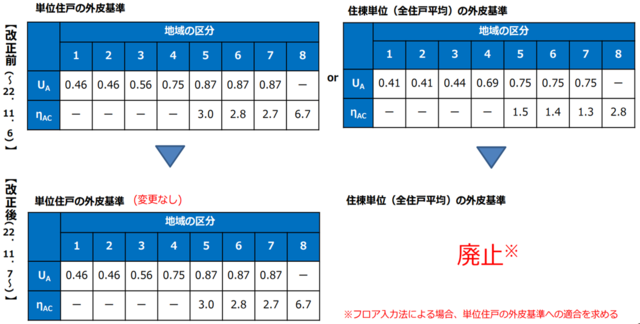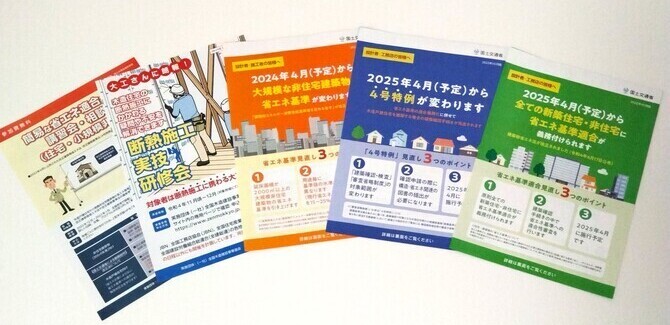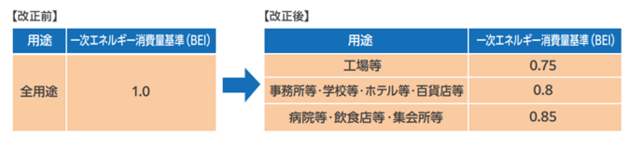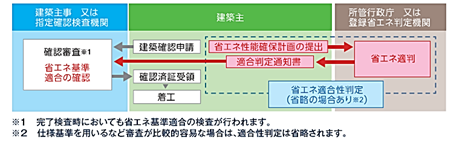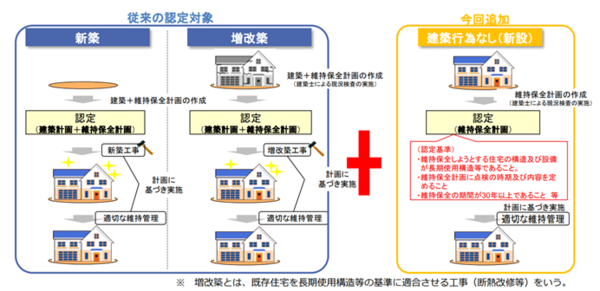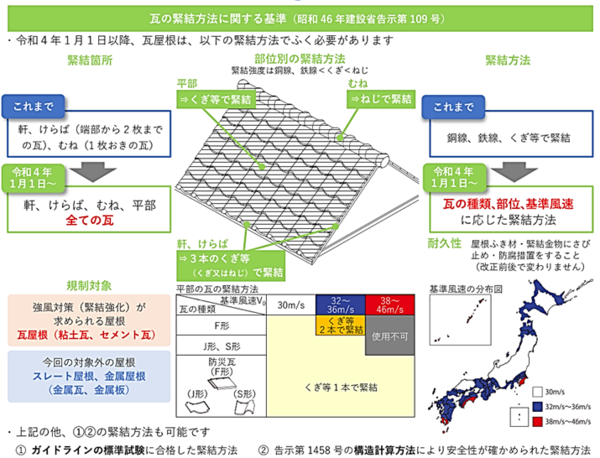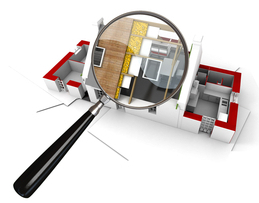建設業に関係する熱中症対策義務化(2025年6月施行)

今年は6月から猛暑の日が多く、熱中症が心配される日々が続いています。
皆様の会社の熱中症対策は万全でしょうか。
令和7年6月1日の改正労働安全衛生規則の施行により、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者の熱中症予防のための対策を講じることが義務化されました。この法規の違反には、罰則が定められています。
【建設業に関係する熱中症対策の義務化と罰則規定について】
令和7年6月1日、新設の労働安全衛生規則612条の2の施行により、建設業等の特に屋外作業が多い特定の条件下で作業を行う事業者に対して、熱中症対策が義務化されました。この熱中症対策は、事業所単位で適用されます。
熱中症対策が義務化の対象となる特定の条件下で行う作業とは
義務化の対象となるのは「WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えた作業が見込まれる作業」です。
まさに建設業、建築・リフォーム関係の作業は該当し、その業務を行う事業主は義務化の対象になります。
熱中症対策は社員に任せたり、教育や指示が曖昧だったり、怠ったりすることは違反となり、事業主つまり経営者の責任で、熱中症対策を行うことが義務になりました。
※WBGT:環境省ホームページ「熱中症予防サイト」に詳細が記載されています。
事業者に義務付けられた内容
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務化されました。
■企業に求められる義務化の内容
➀早期発見のための体制整備
・「熱中症の自覚症状がある作業者」
・「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、
が、その旨を報告するための体制(連絡先、担当者、報告方法)を事業場ごとに定めること。
➁重篤化を防止するための措置の手順作成
作業離脱、身体冷却、水分・塩分の摂取、応急措置、医療機関への搬送、経過観察などについて
具体的な措置や手順を作成すること。
③それらの内容を関係作業者に周知する
すべての作業者に熱中症対策や報告体制について周知するために、
人目に触れる休憩場所などに掲示する、朝礼、ミーティング、社内掲示板活用などを行うこと。
熱中症対策の法規に違反した場合
労働基準監督署からの是正勧告・指導や、労働安全衛生法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
その他、違反による行政処分(指示・命令・業務停止)や熱中症の労災死亡事故による刑事処分の罰則も科されることがありますので、十分な体制整備や対策が必要です。

2025年の熱中症の危険ランク
日本気象協会では、2025年の気温傾向と熱中症傾向を発表しています。
7月から8月にかけては、北陸から沖縄で「厳重警戒」、所々で「危険」ランクになる見込み。
9月は、関東から九州の広い範囲で「警戒」ランクになる見込みであると発表しています。
今年の夏も猛暑で、業務中に熱中症になる危険性があります。
経営者は熱中症の対策と周知を行って、社員や作業をする協力会社の方の健康を守ることが必須になりました。
参考:労働安全衛生規則612条の2(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二
1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
参照:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」