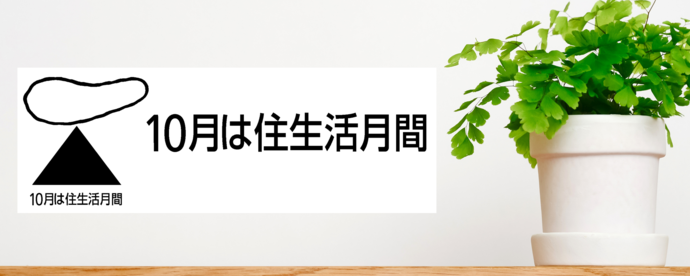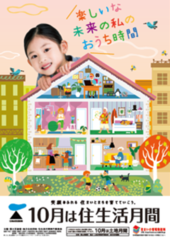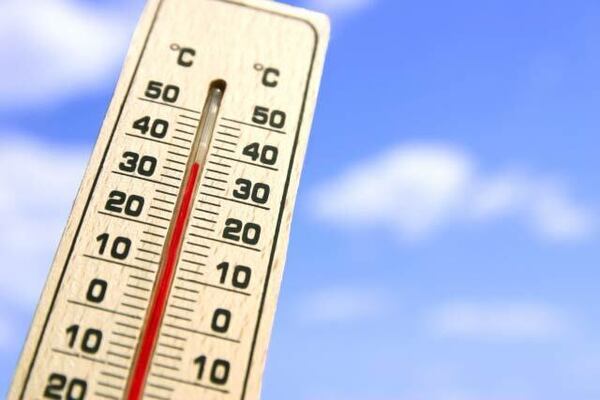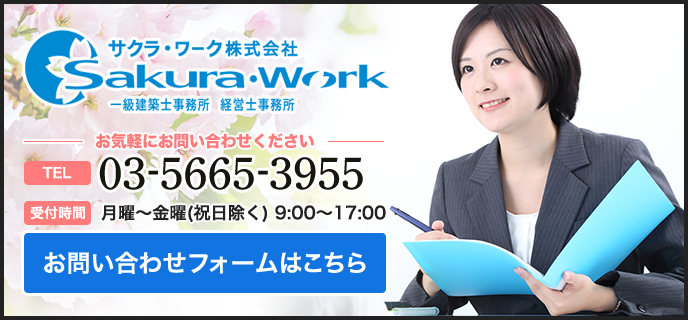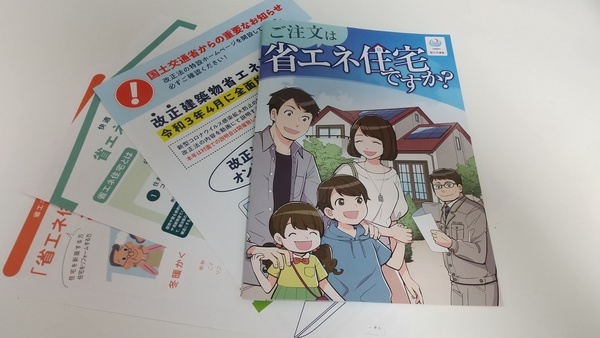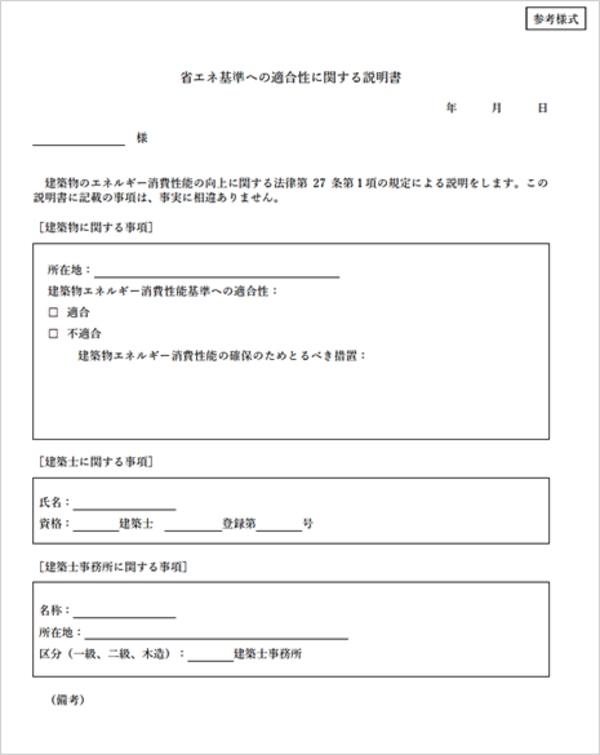10月は木材利用促進月間 中高層住宅や非住宅に木造を普及、地域木材を利用した家づくりの推進

10月は木材利用促進月間
国民に木材の利用の促進についての関心と理解を深めるために、10月を「木材利用促進月間」、10月8日を「木材利用促進の日」として、農林水産省・国土交通省・総務省・経済産業省は、木材利用を拡大するための普及啓発を行っています。
(参照:林野庁ホームページ「10月は「木材利用促進月間」です」)
政府はカーボンニュートラル実現のために建築物に木材利用を推奨
林野庁では、「2050年カーボンニュートラルへの森林・木材分野の貢献」として、「伐って、使って、植える」という資源の循環利用を進め、人工林の再造林を図るとともに、木材利用を拡大することが有効であるとしています。
木材は炭素を長期間貯蔵できるため、建築物に木材利用をすることによってカーボンニュートラルの実現に貢献することを掲げています。
ちなみに、木造住宅は、鉄筋コンクリートや鉄骨造等の非木造住宅に比べて、建築段階の床面積当たりのCO2排出量が約3/5で、エネルギー消費量も少ないため、木造住宅を建築することはエコに貢献します。
法改正で民間建築物を含む建築物一般で木材利用を推進
2010年10月施行の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、法律の名称を「脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わり、一部内容も改正され2021年10月1日に施行されます。
改正内容での注目点は、これまでは木材利用は公共建築物に限定されていましたが、民間建築物を含む建築物一般で木材利用を拡大するとしたことです。
その背景には、木造住宅・建築物の耐震性能や防耐火性能が技術革新によって向上したことや、改正建築基準法による木造建築物の防火規制の合理化により木材の利用の可能性が拡大したことにあります。
そこで、今まで木造化が進まなかった中高層建築物や低層の非住宅建築物、防火地域・準防火地域の住宅・建築物に対して木造を普及し、CLTや耐火部材等の開発・普及を進め、木材活用を普及拡大していきます。
地域の木材生産者、製材工場、工務店の連携での、家づくりを推進
このほか、輸入木材の供給不足の問題もあったため、地域の木材生産者、製材工場、工務店等が連携し、地域で流通する国産木材を利用した家づくりを行う取組も推進していくとしています。
2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の木材の利用促進が拡大されるとともに、安定した木材の供給の仕組みができることを期待しています。
(参照:林野庁「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(改正後:脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律)