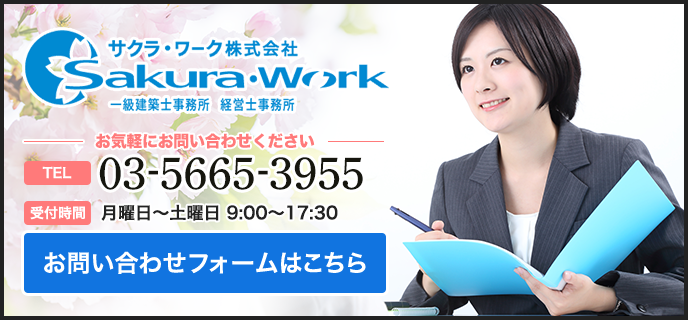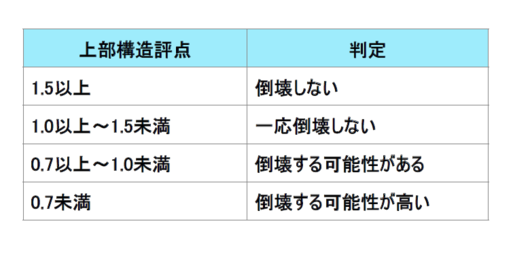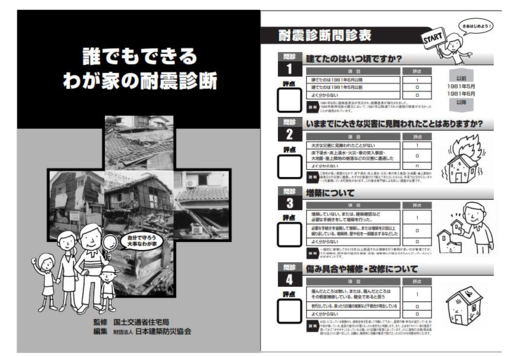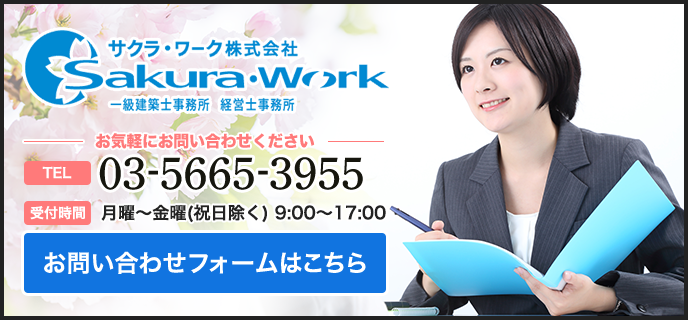お客様にお話したい!営業に役立つ「省エネと宅配ボックス」の関連性

自粛、巣ごもり消費で宅配便の利用率が増加
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、非対面での宅配便の受け取り方式が選択できるようになりました。
社会的な背景もあり、新築・リフォームでも宅配ボックスの需要が増える傾向にあります。特にリフォーム営業の方は宅配ボックス設置をプラスワンリフォームのアイテムとしてお客様に提案されている方が増えています。
確かに今年2月からわが家の買い物の仕方が変化し、緊急事態宣言の終了までは、ネット通販を利用する機会が増え、宅配便によって荷物が届けられることが多くなりました。また自宅でリモートワークを行ったため、書類の送付や荷物は宅配便の利用回数が増えました。宅配業者さんには、大変な時期なのに配達をして下さることに本当に感謝しています。
宅配便の取扱個数が史上最高の増加率

宅配便のヤマト運輸は令和2年5月の宅配便取扱個数が前年同月比19.5%増の1億6498万個、日本郵便のゆうパックは令和2年5月は約9657万個で、前年同月29.1%増となり、「巣ごもり消費」での宅配便利用率が全国的に増加しています。
その反面、令和2年6月26日の国土交通省の発表では、4月の宅配便再配達率は約8.5%となり、調査開始以来最も低い数値となりました。外出自粛による在宅率が増えたことにより、前年まで社会問題となっていた再配達による宅配業者の負担などの問題が緩和されたことを表しています。
非対面の荷物の受け取りは、その方法により不安がある
非対面の荷物の受け取り方で、玄関先への「置き配」は、盗難や不在がわかることで不安を感じる人も多いです。そこで宅配ボックスを設置したい人が、現在増えています。宅配ボックスは設置工事が必要なため、住宅・リフォーム会社が請負って、他のリフォームも兼ねてお勧めするのが合理的です。
ちなみにわが家には宅配ボックスがあるため、配達員さんに迷惑をかけることなく、出かけていても荷物を受け取れることからストレスがなく、本当に助かっています。
国土交通省、宅配便の再配達を減らす省エネ政策を推進
宅配ボックスの設置は、新型コロナ感染症対策により需要が拡大されつつありますが、本来、国土交通省が宅配ボックス等の活用を推奨する目的は、「運輸部門の省エネ」と「配達業者の負担を減らす」ことにあります。
インターネット通販の需要の拡大により、宅配便の取扱個数は、ここ10年間で3割以上増加しています。
そして宅配便による小口配送料の増加に伴って、宅配便のトラックは年間42万トンのCO2を排出しています。しかも荷物の約2割が再配達で、さらにその中の約0.9%は3回以上の再配達を行っているそうです。
そこで再配達は、省エネの視点で考えると、宅配で消費されるエネルギーの25%、つまり原油換算にすると10万KL分使われている計算になります。つまり宅配便の再配達は、地球環境に対して負荷を与ることになります。
また約2割にのぼる再配達を労働力に換算すると、年間約9万人のドライバーの労働力に相当し、社会的損失を与えていることになります。宅配便の再配達問題は、配達業者の負担の増大とCO2排出量問題が大きく係っており、「宅配ボックス」や「置き配」等の推進に繋がっています。
宅配ボックスの必要性は、不在時に荷物を受け取れるという利便性にありますが、それにプラスして地域の省エネ、地球温暖化防止という観点で、再配達を削減するために宅配ボックスの設置についてお客様に話をすることも大切です。
環境省のCOOL CHOICE「できるだけ1回で受け取りませんかキャンペーン」のホームページも参考になりますのでご覧ください。
魅力的な宅配ボックスを営業活動に活用しよう!
戸建用の宅配ボックスは、電気配線工事が不用でなつ印ボタンを押すと押印できるタイプのものや、ホームネットワークとつなげるとスマートフォンで荷物の受け取りや取り出しが確認できるもの、デザインや容量も豊富な製品が出ていて、お客様には魅力的な商材です。
「運輸部門(貨物輸送分野)における省エネ法の改正」にも関連し、消費者側の協力として、新築時の外構プラン、外構リフォームでも今後宅配ボックスの需要がますます増える時代になりそうです。
皆さんの営業活動にもこれからもきっと役立つでしょう。